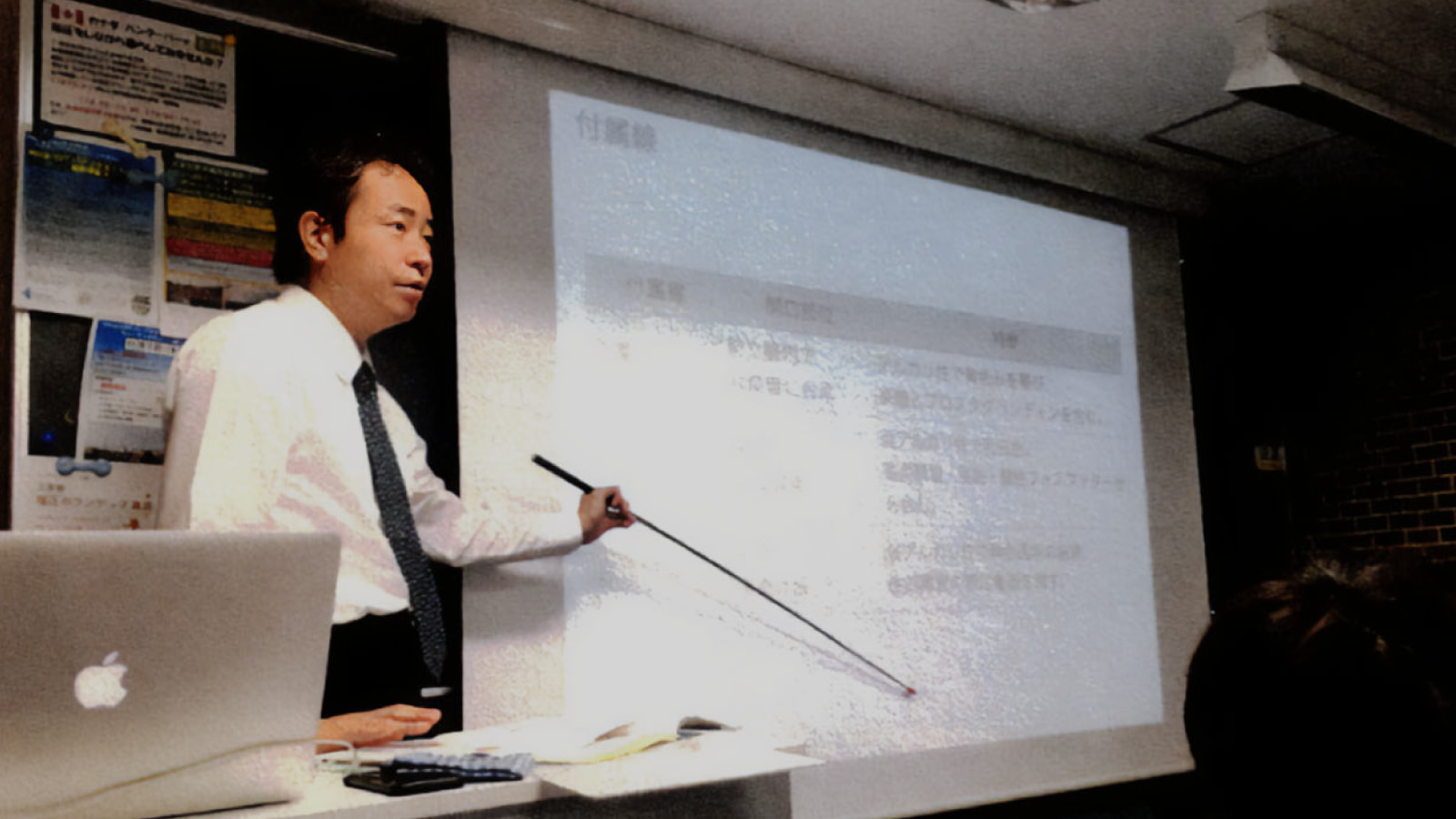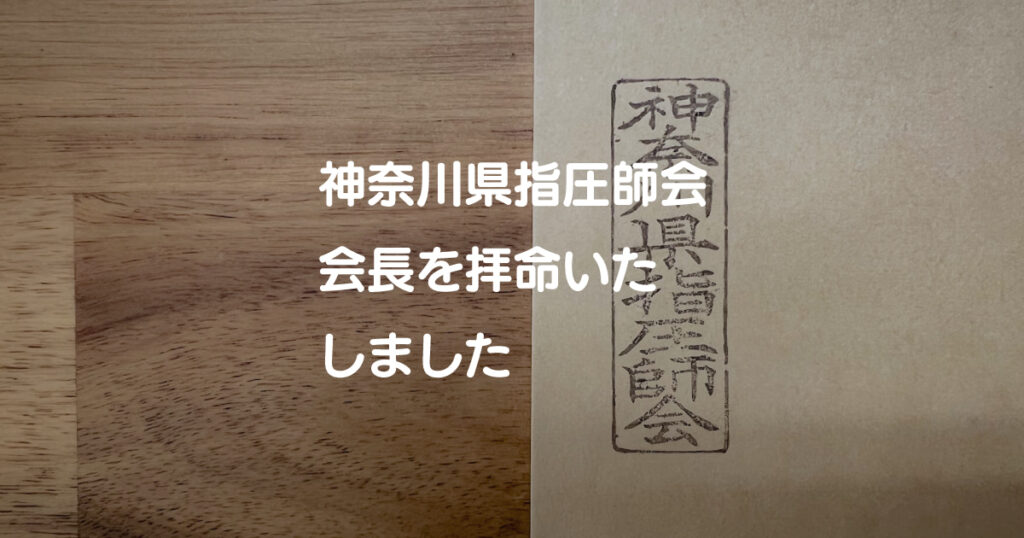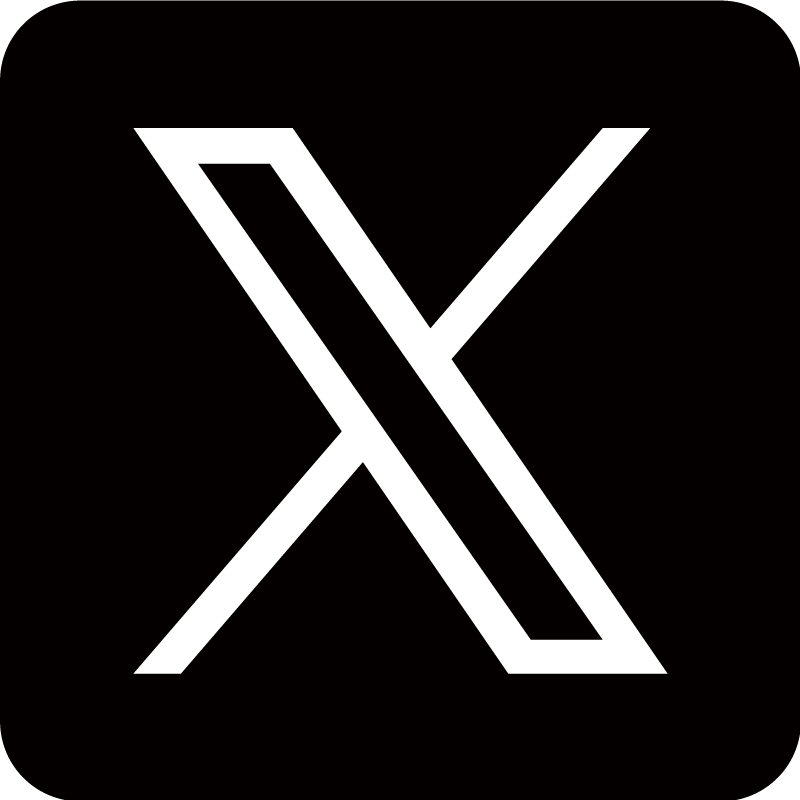お知らせ New Announcements
紡指圧の特徴 Features of Tsumugu Shiatsu
特徴① 伝統的な日本の指圧
Traditional Japanese Shiatsu


紡指圧は日本の伝統的な指圧のスタイルを大切にしています
We respect the traditional Japanese style of Shiatsu.
代表(黒澤一弘)は、文京区の日本指圧専門学校で専任教員として指圧師の教育に従事していました。解剖学と指圧実技を9年間担当し、2019 年に独立。 地元、相模大野で開業いたしました。
浪越徳治郎が体系づけた日本の指圧は、世界的に広まり、欧米で「SHIATSU」とそのまま通じるほどです。私たちは日本の伝統的な指圧のスタイルを大切にし、心をこめた施術で地域の皆さまの健康に貢献いたします。
特徴② 心地よい畳の空間
Comfortable Tatami Space


広い畳のスペースは風通しもよく、手足を自由に伸ばせるので、心からリラックスできます。
You can stretch out your arms and legs and relax from the bottom of your heart.
紡指圧の店内にはいると、広々とした28畳の畳のスペースが広がります。爽やかな風通しの良さを大切にし、あえて固定壁やカーテンでしきらないオープンスペースにしています。
広い畳は道場も兼ねています。 神奈川県指圧師会の研究会会場として使用している他、指圧療法を学びたい方々や、あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師、養成校の学生向けの指圧セミナーや練習会も定期的に行なっています。
特徴③ 解剖学に精通
Anatomy-Savvy Therapist
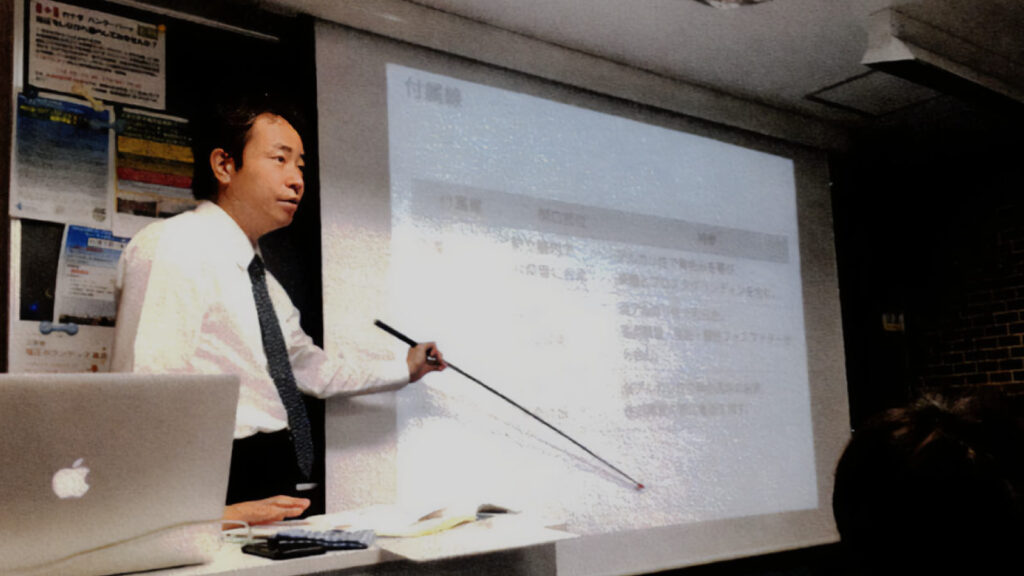
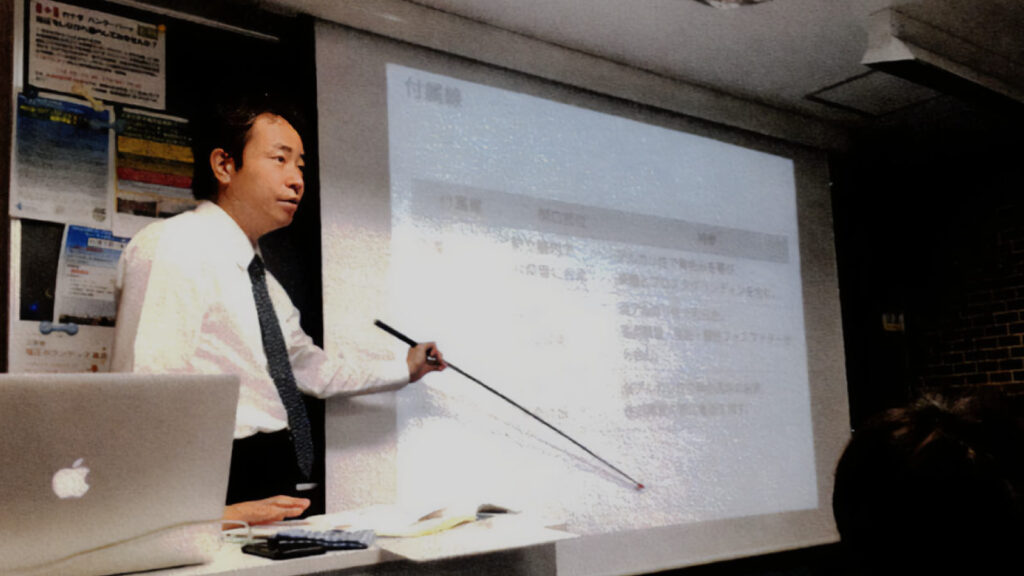
黒澤一弘は医療系学生の解剖学講師として活動中。「かずひろ先生」SNS総フォロワー5万以上。大学で解剖学実習の非常勤講師も行っている解剖学の教育者です。
“Kazuhiro Sensei” is well-known for anatomy among medical students and has a total of over 50,000 followers on social media. He is an educator in anatomy who also serves as a part-time instructor for anatomy practical sessions at the university.
Instagramでは作成した解剖学資料をInstagram用に正方形にして公開しています。解剖学学習を身近に、電車内などスキマ時間で勉強にできるように工夫しています。
X(Twitter)では、あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師、医療系学生さんとの交流や、資料の公開、勉強法など元教員の指圧師目線で発信しています。
特徴④ 温熱と指圧の組合せ
The fusion of thermotherapy and shiatsu.


温熱瓦「長久」
thermo-kawara “Choukyu”
タオルに包んで使用します。多孔質のセラミックから伝わる上質な湿熱が心地よいです。


ベン石温熱器
Bian Stone heat gua sha
ベン石は泗濱浮石とも言われ、中国山東省の泗水流域で採掘される石です。
指圧施術と組み合わせて温熱を効果的に用いています。身体をあたためると毛細血管が開き循環がよくなるとともに、緊張した筋肉がはやく柔らかくなっていきます。 温熱刺激と押圧を同時に組み合わせることにより、 身体の深部の冷えに対して効果的です。
内臓の冷えによる不定愁訴はつらいものです。心地よい指圧に温熱を加えることで、身体内部からぽかぽかして、疲れた心身を癒すことができます。
特徴⑤一期一会のもてなし
One-time, one meeting hospitality


“One-time, one meeting hospitality” is a Japanese concept that emphasizes treating each encounter with a customer or guest as a unique and special opportunity, providing the best service and care in that particular moment.
私たちは一期一会を大切にし、ご来店いただくお客様との機会や瞬間を唯一のものと考え、最善のもてなしを提供するように心がけています。
慌ただしい日常からほんの少し離れたところで、心からリラックスをしていただき、安心のうえに信頼を重ねて、ひとおしひとおし心をこめて指圧をさせていただいています。
コースと施術料金 Course and Treatment Fees


指圧コース(予約制)
Shiatsu course
浪越式の全身指圧療法を主体に、温熱療法(温罨法)を適宜組み合わせて行ないます。当店では局所のみの施術は極力おこなわず、全身を指圧させていただくことにより心身の状態を良くしていきます。
・60分:6,000円
・90分:8,000円(おすすめ)
・120分:11,000円
※ コースはすべて施術時間です。問診やお着替え、施術後のアドバイスなどでコースの時間+20分ほどかかります。
スペシャル温熱指圧(温罨法)コース(予約制)
Special Thermotherapy Course
・60分:12,000円
・90分:16,000円
・120分:22,000円
※ 施術者2人で行ないます。通常の指圧コースでも温罨法は併用いたしますが、スペシャル冷え取りコースでは施術者2人で対応いたしますので、よりきめ細かい温度管理や施術を行うことができます。つらい冷え性にお悩みの方や温熱療法(温罨法)をしっかり受けたい方におすすめです。
アクセス Access
小田急線相模大野駅より徒歩7分


紡指圧(つむぐ指圧治療室)
神奈川県相模原市南区相模大野5-27-39
和田ビル2階
042-743-3933
【電車でお越しの場合】
最寄り駅:小田急線相模大野駅(新宿より快速急行で約40分)
ロビーシティ前交差点を相模女子大方向に進み、向かって左側「もみやま耳鼻咽喉科さん」と「大学堂薬局さん」の間をななめに少し入ったところです。(相模大野駅より徒歩7分)
【お車でお越しの場合】
専用駐車場はございませんが、ロビーファイブ地下駐車場が広く、値段も安い(30分150円)のでお勧めです。
ご予約・お問い合わせ Reservation and Inquiry
LINEでお問い合わせ Contact us on LINE
おすすめのお問い合わせ方法です。時間を気にせず、いつでもお問い合わせいただけます。
なるべく迅速にお返事をするよう、心がけています。
メールでお問い合わせ Contact us by email
メールの場合、意図せずに迷惑メールフォルダに振り分けられてしまったりする可能性があります。
お問い合わせを頂いたときには、なるべく早くお返事をするように心がけていますが、2日以上たっても連絡が付かない場合、迷惑メールに振り分けられてしまったり、メールが送受信できていない可能性があります。
その場合、LINEか電話でお問い合わせいただきますよう、お願い申しあげます。
電話でお問い合わせ Contact us by phone
施術中は電話に出られない場合がございます。また、営業時間外やお休みの日も電話にでることができません。
たいへん申し訳ございませんが、着信履歴からの折り返しはしておりませんので、電話が通じない場合は時間をおいて再度ご連絡をいただくか、LINEやメールにてお問い合わせください。
業者様など、電話での営業やサービスの提案などは全てお断りをしています。